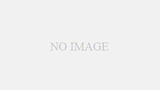前回の記事では「やたらビジネスで流行る言葉=ビジネス新語」として、
少し前からよく聞く「ジョブ型雇用」「SDGs」「人生100年時代」について考えてみました。
どの言葉もメディア、Twitter、上司同僚と
もう生きているだけで四六時中聞かされる話です。
どれも時代の流れの中でスポットライトを浴びている言葉ですが、
そこに襲うは流行の宿命。
あまりにも流行りすぎた結果として言葉が独り歩きしてしまい、
「SDGsのバッジをつけたおじさんがウナギを食べに行く」事件が起きたり、
「お金だけでなく家族や友情、スキルといった無形資産を大切にしよう」と言っていた
“人生100年時代”がいつの間にか「老後2,000万問題」になって大炎上したりしました。
どうしてこうなった。
「デジタルトランスフォーメーション」は「ハンコ廃止」なのか
そんなこんなで流行りというものの持つ力とその恐ろしさを身にしみて味わっているところですが、令和の大ブームといえばそう「DX」です。DXと書いてふつうにディーエックス、
または元表現の「デジタルトランスフォーメーション」と読みます。
デラックスではありません。ダブルエックスでもありません。月は出ているか?
ところで今日皆既月食らしいですね。なぜこんなしょうもない奇跡が・・・
この言葉の世の中におけるイメージは、
「ハンコ廃止」
「紙を電子化にする」
そして本丸の「ビジネスにおける様々なものをデジタル化する」といった印象でしょうか。
長らく多少なりとも取り組んできていた人間としては
既にこの時点で「どうしてこうなった」感が半端ないですが、
それだけ身近なものと結びついたということで、
世の中のニーズとこの分野が近づいてきたということでしょう。
ご存知の通り多様な意味を含む言葉ですので、
今回はあくまでマーケティングにおけるDXという位置づけですが、
この言葉について改めて考えてみたいと思います。
読んでいく本はこちら。
あのセールスフォース・ドットコムに創業期から入社し、
CMO(最高マーケティング責任者)やCSO(最高戦略責任者)を歴任、
要するに実務をめちゃくちゃ取り仕切っていた世界最高クラスの仕事できる人、
ティエン・ツォさんの著書
「サブスクリプション 「顧客の成功」が収益を生む新時代のビジネスモデル」です。
今となってはZuora(ズオラ)の創業者と言ったほうが有名かもしれません。
この本は21世紀のビジネスにおける基礎教養として必携の一冊だと私は思っていますが、
その肝は表紙裏に書いてある一言かと思います。
モノが売れず、すべてがサービスとして提供される時代には、こちらですね。
顧客との長期的なリレーションシップが成長の鍵となる。
「サブスクリプション」というタイトルと切り口ですが、
「サブスクビジネスやろうぜ!儲かるぜ!」という話ではなく、
ビジネスの潮流がどう変わってきていて、これからはどうビジネスをすれば生き残れるかという大きな流れに着目した“考え方”の本です。(※ノウハウ本などでは全くない)
すでに「変わっている」世の中
そしてデジタルトランスフォーメーションですが、「これから変化を起こしていこう!時代を変えていこう!」というよりはとっくに変化は起きて世の中は変わってしまっている中で、自分たちのビジネスはどうしていこうかというスタンスで臨んだほうがより実状に近いのではないかと思います。
ここで読者にたずねたいことがある。そういえばOfficeも365になったなあ、仕事で使っているシステムももうSaasばかりだなと改めて感じました。もはや買い切り型のほうが珍しくなっているのではないでしょうか。
クレジットカードの利用明細のうち、財布からカードを出さずに行った利用分の請求はどのくらいあるだろう?
たぶんネットフリックス(Netfrix)やスポティファイ・プレミアム(Spotify Premium)から毎月の請求があるのではないだろうか。
(略)
仕事で使っているパソコンはどうだろう?
いまだに立ち上げ時にチャイムが鳴り、デスクトップに丘の風景が現れる古いOSだったりするのだろうか。
(略)
そんな環境でないことを願うが、さすがにもっと洗練された環境になっているのだろうと思う。
ログインは1度だけ、ごく軽いアプリケーションが2つか3つ、あとはブラウザだけ。
会社がEメールのホスティングをGメール(Gmail)に切り替えていれば、半年ごとにアウトルック(Outlook)の古いファイルを削除する手間もなくなっているかもしれない。
会社の全ファイルがボックス(Box)に収納されるようになり、かつてのサーバールームでは社員が卓球をして遊んでいるかもしれない。
すべてがこれまでと様変わりした。
なぜか?
いまがビジネスの歴史の重要な転換点にあるからだ。
産業革命以後、見られなかった転換である。
一言でいえば、世界の中心が製品からサービスに移行しつつあるということだ。
(p2-3,ティエン・ツオ,ダイヤモンド社,2018)
※用語
Nintendo SwitchだってPS5だってXboxだって、
月額課金による特典享受がスタンダードになりました。
定期的に紹介している「Nintendo Switch Onlineで遊べるファミコン・スーファミゲーム」は
まさに典型的なサブスクリプション・サービスですよね。
こうして振り返ると、どうやらずいぶん前から世の中は変わってきていたようです。
デジタルトランスフォーメーションにより「モノを売って終わり」が通用しなくなる
そしてこの転換を理解するのに大切な概念が「デジタル・トランスフォーメーション」なのです。読んでいきましょう。
デジタル・トランスフォーメーションとは何か?この「ハードからソフトへ」みたいなのはもう何年もすごく言われている部分ですよね。広告代理店に言わせれば「モノ消費、コト消費、トキ消費…」
まず、それがきわめて曖昧な用語だということを認識しておく必要がある。
カンファレンスやマッキンゼー・レポート、『ハーバード・ビジネス・レビュー』などで見聞きする、賢そうに聞こえるビジネス新語で、意味が分からなくても多くの人が思わずうなずいてしまう言葉。
なんでも好きな意味を持たせられそうだが、何も意味していないかもしれない言葉だ。
私が考えるデジタル・トランスフォーメーションの意味はこうだ。
2000年にフォーチュン500に入っていた企業の半分以上が今では存在しない。
この数字は見たことがある人も多いのではないだろうか。
合併、買収、倒産の結果、多くの企業がリストから姿を消した。
1975年にはフォーチュン500企業の平均寿命は75年だったが、今では15年だ。
なぜこんなことになったのだろう。
失敗の原因を探るため、消え去った企業にではなく、生き残っている企業に目を向けてみよう。
1955年に発表された第1回目のリストには、GEやIBMといった製造大手の名前が見られるが、両者とも今日、メインフレームや冷蔵庫、洗濯機について語ることはない。
代わって「デジタルソリューションの提供」を強調している。
それはこの業界一流の言い回しで、
「ハードウェアは目的を達成するための手段である」ということを意味している。
言い換えれば、彼らは自社の装置を売ることにではなく、
それを使ってクライアント企業が得るものに焦点を合わせているということだ。
(p26-27,ティエン・ツオ,ダイヤモンド社,2018)
とはいえ「確かにIBMやGEはそうかもしれないけど、でもウチは…」と思われるビジネスパーソンの方も多いかと思います。
ここでのポイントは、シンプルに「ハードからソフトへ」という話なのではなく、「自社の装置を売ることにではなく、それを使ってクライアント企業が得るものに焦点を合わせている」の部分です。
何が言いたいかと言うと、極端な言い回しをすれば
「物を売ってそれで良し」の時代が終わって、
「お客さまが物を買いたかった理由と、
物を買っても実現できなかったことやその理由をしっかりと理解して、
それを叶えてあげるところまでやらないとビジネスが成り立たない」時代になったということです。
本書の表現をお借りすれば、
顧客一人ひとりが異なる顔を持っているということを認識し、ということになります。
その認識の上にビジネスを構築して成功している
(p30,ティエン・ツオ,ダイヤモンド社,2018)
つまり、顧客を理解できる時代になった、理解しなければビジネスにならない時代になった(競合に負ける)、というのがマーケティングにおけるデジタルトランスフォーメーションの本質なのです。
なぜデジタルの時代になってこのような変化が起きたかというと、とてもシンプルな話でデータが取れるようになったからなのですね。
それはいわゆる顧客ID管理でのCRMによるデータ収集でもそうですし、
もっといえばサブスクビジネスは個々の利用状況まで詳細に把握できるので、
そうしたデータを持つ企業は顧客が喜ぶサービスを提供することに有利となります。
サブスク系企業がぐんぐん伸びているのには、
定期契約という形態以上にこのあたりの上手さがあるのでないでしょうか。
しょうもないものを人は定期契約しないですからね。
この辺り、いわゆる「賢明な顧客」の登場が企業に手抜きをさせない良い緊張感を与えているのではないかと思います。
他人事のように顧客を扱っていれば事足りた、権威ある企業の栄光の日々は去って久しい。
今日の顧客は、かつての顧客の何倍もの情報を持っている。
彼らのほとんどは、企業が「ようこそ、わが社へ」と言っているあいだに企業を研究し、評価し、選り分けてしまう。
(略)
そして、面白いことが起きた。
すでに言及したセールスフォースやアマゾンのようなデジタル世界の破壊者たちが、
顧客との間に真に直線的かつ継続的な関係を確立することによって
顧客ファーストのコンセプトを大きく前進させたのだ。
彼らはセグメントに分けた顧客を相手にせず、
一人ひとりのサブスクライバーと向き合ってビジネスを行っている。
個々のサブスクライバーには、自分のホームページがあり、購買や閲覧の履歴があり、
これ以上は我慢しないという基準があり、自分なりの理屈に基づく主張があり、
ユニークな経験がある。
その一方で、サブスクライバーIDのおかげで、
POSプロセスでのトランザクション管理という退屈な仕事は消滅した。
10年前、スポティファイは存在せず、
ネットフリックスはDVDレンタル企業だったが、
いまや両社はそれぞれの業界の総収益のかなりの割合を占める収益を上げている。
こうした状況の下、今日の企業はまったく新しい一連の問いを自問し始めている。
・顧客と長期的な関係を築くために何をすればよいのか?
・所有ではなく結果を期待する顧客に何をすればよいのか?
・どうすれば新しいビジネスモデルを生み出せるのか?
・どうすれば顧客に継続的な価値を提供し、定期収益を増やせるのか?
以上を踏まえると、デジタル・トランスフォーメーションはどのように見えるだろう。
(p33,36,ティエン・ツオ,ダイヤモンド社,2018)
DXに「うちは関係ない」業種はない。フェンダーギターの事例
この「一人ひとりの顧客に着目し、顧客の求めるものを叶える」ことが肝なデジタルトランスフォーメーション。「ウチは関係ない」ではなく、これは全ての業界における破壊的変化と可能性です。
今日の最後はテクノロジーやコンテンツ以外の業界でのDXについて。
本書で紹介されているギターの「フェンダー」は非常に分かりやすいと思います。
フェンダー(Fender)の事例が素晴らしい。要するにフェンダー・チューンアプリで顧客のギターの使用状況を確認し、
彼らは70年以上にわたり素晴らしいエレキギターを作ってきた。
しかし、業界全体の売上は過去10年で約3分の2にまで減少している。
また、フェンダーの売上のほぼ半分は初めてギターを持つ初心者で、その90%が1年以内にギターに触るのをやめてしまう。
その原因は、フェンダーのCPO(最高製造責任者)であるイーサン・カプランによると、ギターが「マスターするのが難しい楽器」だからである。
いくつかコードを覚えるぐらいまでは簡単だが、その先が難しく、ほとんどの人がギターを弾くのをやめてしまう。
しかし、そこを乗り越えて演奏を続けて貰えれば、そのほとんどが生涯の顧客としてとどまってくれるとカプランは考えている。
ギブアップする人の比率を抑えることが重要な優先課題であり、
それは「電源に接続されたギター」について考えるだけでは実現しないこともわかっていた。
そこで、彼らはギター初心者が最初のリフや曲を30分程度でマスターできるよう指導する、フェンダー・プレイ(Fender Play)という定額利用のオンライン教育動画サービスを開始した。
(略)
「われわれは視聴者をしっかり理解するためにセグメンテーション分析を行った。その結果をデジタル戦略を展開するための手がかりとして使った」とカプランは説明する。
(略)
2016年8月には、フェンダー・デジタル(Fender Digital)の最初の製品としてチューニング用の無料モバイルアプリの「フェンダー・チューン」(Fender Tune)を発表した。
フェンダー・チューンはフェンダー・プレイの利用者がぶつかる壁を取り除くのに役立ち、膨大な消費者データの活用を早めた。
「何分かけてチューニングしているか、何人がチューニングしているか、どの機種をチューニングしているか、うまくチューニングできたかなどがわかります」とカプランは言う。
彼のチームは、フェンダー・プレイを発表する前に、フェンダーのデジタル製品全体からリアルタイムのインサイトを得るために、1年かけてデータ分析の仕組みとダッシュボードを構築した。
カプランは次のように語っている。
「学習を通じて顧客と継続的に対話することが重要だ。
私は客にただギターを売って、やめないでくれと願うだけのビジネスはしたくない」
フェンダーのアンディー・ムーニーCEO(略)は、
ギブアップ率を10%削減するだけで、同社の売上を倍増させることができると述べている。
(略)
顧客をギターの所有者として見るのではなく、
ギター奏者として、生涯にわたる音楽愛好家として見るということだ。
「創業者のレオ・フェンダーは、実はギターを弾いたことがない。だが、彼はアーティストの声に耳を傾けた。
フェンダーで、私たちはいまも顧客の声を聞くことの重要性を信じている」とムーニーは語った。
(p33,36,ティエン・ツオ,ダイヤモンド社,2018)
どこで躓くかを把握して、顧客がギターをマスターできるようになるサポートを行っていくというお話ですね。
自社の持続可能な成長のためには「ギターを挫折せず楽しんでもらうこと」が大事だという仮説を立て検証し、そしてそのためのアクションを行っていく。
根本的なところには、ムーニーCEOが仰っている創業からの精神があるのではないかと思います。
この例は、デジタル・トランスフォーメーションの時代になって出来るようになったこと、そしてビジネスをする上で私たちが目を向けるべきこと、取り組まなければならないことについて大きな学びを与えてくれます。
マーケティングにおけるDXの本質は商売の基本に根差したもの
情報社会とデジタル技術によって、顧客は企業を選べるようになりました。競合との比較ができるようになりました。
本当の顧客志向を持ちましょう。お客さまのことを考えましょう。
そしてお客さまのことが見えていなければ、それだけで大きなビハインドです。
どうデータを収集すればよいかを考えましょう。そのためにデジタル技術を活用しましょう。
売ったもの勝ちではない。「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」。
そんな商売の基本こそがマーケティングにおけるDX、デジタルトランスフォーメーションの本質ではないかと私は思います。