ゲームを続ける理由ってなんでしょうか?
とくにソーシャルゲームを念頭に入れて思い浮かべてみて下さい。
もちろん、自分が楽しいから遊ぶというのが基本だとは思うのですが
本当にゲームが楽しいからゲームを続けているのでしょうか?
今回はゲーム継続に影響を与える人間の「同調効果」について考えてみます。
前回の続きで、橋本先生の行動経済学の本を読んでいきましょう。
行動経済学の”保有効果”:あなたの500円のマグカップ、いくらなら売るか | ゲームと子育て 時々にどね(にどねゆうき ブログ)
ゲームはSNS的な交流との関係が深い
自分を貫ける人間は多くないさっそく内容です。
ゲームの結果や経過を共有することは、他の人との「つながりを作る」ために役立つ。(橋本,2014,p40)
「つながり」まさに。ゲームBlogとゲームTwitterをやっている人間としては心から共感します。
話のネタにもできるし、直接会っていない友人の行動が分かる。ゲーム結果のスコアや、攻略したステージが明示されていれば、友人との比較も簡単だ。本当ですよね、私などパワプロもAPEXもポケモンも、つい毎回シェアしてしまいます。
また、スコアのランキングがあれば、参加者の中でどのぐらいの位置にあるかも一目でわかる。良い成績であれば、自分が高い評価を受けたことを自慢できるだろう。
良い意味での競争関係が、ゲームを頑張ろうと思うモチベーションを生むかもしれない。(橋本,2014,p40)
にどねゆうき丨✒ゲームBlog@sw32551
やったー!!!中日ドラゴンズのLIVEシナリオスコアランキングで全国59位!!全球団ではまだまだだけど、ひとまず嬉しい!!!
#パワプロ2020 #パワプロ #Pawapuro #NintendoSwitch https://t.co/2rF65LXQmh
2021/04/11 18:35:51
にどねゆうき丨✒ゲームBlog@sw32551
あさペックス一試合目でまさかのチャンピオンに!!
チームメイトの方が強すぎて…!!!全員生存、ダウンゼロと完全勝利。おまけに最後のひとりもキル!朝から最高!!!! #NintendoSwitch https://t.co/pEuHgU0IzF
2021/04/11 10:55:04
にどねゆうき丨✒ゲームBlog@sw32551
#ポケモンGO の #コミュニティデイ 、朝からツタージャ30匹も捕まえた〜!!😊生態系への影響が危ぶまれる。
色違いツタージャも捕まえたし満足😆😆 楽しかった〜!! https://t.co/zYmDw88RVZ
2021/04/11 11:49:11
人には「同調効果」というバイアスがある
一方、ゲーム時間を延ばすために、また戦う場面において、共に協力し合うような場面もある。こうして他人の存在を感じられるようにすることや、つながりを体験させることも、ハマらせる仕組みのひとつだ。この同調効果というのは実験でも証明されています。
人間は、自分の判断で行動しているつもりで、実は他人の影響を受けていることが多い。
他人の影響や選択を見て、自然に同じ行動を取ってしまうのだ。
特に選択や判断が難しい場合に、これを自分の決定の根拠とする場合も多い。
しかし当然ながら、見る相手の判断が正しいとは限らない。
このような、人と同じ行動を取ってしまう、判断におけるバイアスを「同調効果」と呼ぶ。(橋本,2014,p40)
8名の集団の中に放り込まれ、自分以外の7人(サクラ)が明らかに誤ったことを言っている。すると3割ほどの人はその明らかに誤っている答えを選んでしまうというんですね。
これがまさに「同調」によって行われた判断です。
同調効果で「人がやっているから」ソシャゲを続けてしまう
こうした人間の同調効果を特にうまく使っているのが「ソーシャルゲーム」、いわゆる「ソシャゲ」です。(前述の実験の紹介を経て)このように人間の判断は、他人に左右されるものである。「かつて」であればモバゲーやGREE。(今どうなったんだろう?)
例えば、あるソーシャルゲームにハマっている人がいたとする。そのゲームが、こまめな空き時間でできるとしても、気が付くとかなりの時間を費やしている。また、細かなアイテムを購入するにつれて、結構な出費もしている。
これ以上ゲームを続けるのはもしかしたら無駄なのではないか?と考え、止めようかどうしようかと考える。
これが、他人とのつながりのないゲームであれば、純粋に自分の判断だけで決断できるだろう。
しかし、ソーシャルゲームの場合は、同じようにゲームにハマっている人が数多くいる。
しかも、その人たちとはプレイを共有し合ったり、競い合ったりしているのである。
そこで「同調効果」により、自分の判断が影響されても不思議はない。
止めなければならない確固たる理由がないのであれば、他の皆がプレイしているように、今まで通り続ける選択をしても不思議はないのだ。
こういった自分以外のプレーヤーの存在も、人をソーシャルゲームにハマらせる要因の一つなのだ。(橋本,2014,p42)
現代のソシャゲというと、ガチャのついたスマホゲームという印象があります。
しかしながら、橋本先生の文章を読むと、ソーシャルゲームの肝は「プレイを共有し合ったり、競い合ったりしている部分」。社会的な交流、すなわちSNS的な交流ですね。
そういう意味では、オンライン通信機能のついた多くのゲームも今やソシャゲ的な一面を持ち合わせているのかもしれません。そもそも本体にSNSとの連動機能がついているので、あらゆるゲームが部分的にソーシャル化しているともいえます。
とくにプレイをTwitterやYoutubeで共有している方にとってはそうでしょう。
そうなってくると、あらゆるゲームを続ける理由には同調効果の影響が関わってくるともいえます。
いま自分がやっているゲームは、自分が面白いからやっているのか??それとも付き合いでやっているのか??訳が分からなくなってきます。
本当に自分はゲームを楽しんでいるのでしょうか。やらされているのでしょうか。同調効果に踊らされて、惰性的に付き合いで続けているだけではないのでしょうか。
ソーシャルゲームをするとき、純粋に楽しんでいるだけではなく、こうした同調効果が自分にも働いている中で遊んでいるということは認識しなければなりません。
しかし同調効果があるからゲームは危ないのか?
なんかこんなふうに書くと「ソシャゲ怖い!惰性!」となりそうですが、プラスに捉えてもいいと思うんですよね。そもそも草野球とかゴルフとかみたいな趣味って、社会的な交流が醍醐味みたいな部分があるじゃないですか。別にそこらへんのフレッシュ新入社員くんがマスターズ優勝目指しているわけではないですし。(松山選手おめでとう!)
ゲームも趣味なわけですから、そういう意味でつながることが得意な趣味、つながりが組み込まれた趣味という要素があるともいえるわけです。ゲームからつながりが生まれる!!
前にまじめな記事でディスタンクシオンをヒントに「ゲームは経済資本と文化資本を乗り越えて世界平和の救世主になるかも」と書きました。
まじめ)ゲームは分断が広がる世の中での救世主かもしれない | ゲームと子育て 時々にどね(にどねゆうき ブログ)
ハードルの低さと奥深さ、さらに社会性をあわせもったゲーム。
うまく社会に適合できない方にとっての「社会とのつながり」としての役割や、また「社会復帰への階段」にゲームがなれる可能性だってあるんです。
確かにゲーム×ソーシャルは同調効果が強く発揮され、付き合いで続ける可能性が爆発的に上昇し、時間ドロボウとして非常に危険かもしれません。
ですが用法用量を守って使えば「社会と繋がれる何よりも楽しい趣味」になるという面を持っているとも言えるわけです。
どんなことでもメリデメは表裏一体。
きょうもみんなで楽しくゲームしましょう。



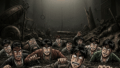
コメント