ITストラテジスト試験を受験してきました!
本日、情報処理試験のひとつ「ITストラテジスト試験」を受験してきました。
この試験の恐ろしいところはとにかくそのボリューム。短答+短答+長文読解&記述+論文という4種類の試験を1日で受けます。終わるころには日が暮れる勢いです。めちゃくちゃきついです。
私は幸い、昨年の秋の試験で「応用情報情報技術者試験」という1つ低いランクの試験を合格していたので、規定により4つある試験のうち“午前Ⅰ”が免除になっていたのですが、それでも長時間の試験は本当にきつかったです…。終わったらラーメンでも食べようと思ったのですが、心身ともに疲れ果てていて胃もたれしそうなので、冷やし中華にしようと思います🥺
受験をされた皆さま、本当にお疲れさまでした😊😊
生成AI(gemini2.5pro)を使って、午前Ⅱ試験の解答速報を作成してみる
さて、試験も終わったのでご褒美(?)の自己採点でもしようかなと思っていたら、IPAはもちろん、なんと資格の予備校TACの解答速報でも4/23(水)の夕方の開示になるそうです。
解答速報 令和7年度春期 情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験|情報処理|資格の学校TAC[タック]
私はとくに転職などは考えていないので、資格を必ずしも取らなくてはいけないわけではなく、勉強をしようと考えたのは何より自分の力をつけるため。そのため、復習もとても大切です。
そのモチベーションが一番高い試験当日に自己採点と振り返りが出来ないのはもったいない・・・ということで、2025年ですので生成AI(gemini2.5pro)に試験を解いてもらい、解答速報を作ってもらってそれを見て勉強することにしました!
私個人の学びのためのものですが、こちらに出力内容を貼り付けさせて頂きますので、よろしければご活用ください。なお、皆さまご存じの通り生成AIにはハルシネーションが発生し得ますので、あくまで参考としてご覧ください。試験後の疲れ果てた頭で「へーそうなんだ・・」というテンションで見てますので、裏取りなどまったくしていない一発出しです。
もし検索か何かでアクセスされた方は、2025/4/23以降であれば先ほどのTACのWEBサイト、IPAで解答速報がすでに発表されているようであればそちらをご覧ください。以下のページに公開されるのではないかと思います。
使い物になる解答はおそらく午前Ⅱぐらいだろうというのと、午後Ⅰの問題文をgeminiに渡す気力がないので午前Ⅱのみを生成してみます。なお、午後Ⅱの論文のときによくやっていたのですが、問題文と採点基準、自分の設計図(できれば論文)あたりをgeminiに渡すといい感じに採点くれますのでよろしければお試しください。せっかく書いたので楽しみましょう🤭
4/20(日) 20:06追記
ってスマホからTACのサイトをよく見たら「午前Ⅰと午前ⅡはIPAのWEBサイトに解答あるから見てね」って書いてある!!PCにも書いてよ!!
勉強になったので一切後悔はないですが、二回も自己採点をするハメになりました。みんなIPAのサイトを見よう。

そしてgeminiの解答全問合ってました。さすがです。安心して見てください。
4/20(日)21:02追記
せっかくなので午後Ⅰの解答速報もgeminiに考えてもらいました。それっぽくてももちろんこちらは絶対に合っていません(文章題だし)ので、お遊びとしてご覧ください。振り返りの観点に。
令和7年度(2025)ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 解答速報 ※生成AI作成
以下、午前Ⅱ試験の解答を一覧にさせて頂きます。すべてgemini2.5PROが作成しています。
(※20:10追記:IPAの解答速報と私が見比べたら全問合ってました!)
| 問題 | 解答(gemini) |
| 1 | エ |
| 2 | ウ |
| 3 | エ |
| 4 | ア |
| 5 | エ |
| 6 | ア |
| 7 | ウ |
| 8 | イ |
| 9 | エ |
| 10 | ウ |
| 11 | エ |
| 12 | ア |
| 13 | ウ |
| 14 | イ |
| 15 | ア |
| 16 | ウ |
| 17 | ウ |
| 18 | ウ |
| 19 | エ |
| 20 | ア |
| 21 | イ |
| 22 | エ |
| 23 | エ |
| 24 | ウ |
| 25 | エ |
geminiによる解答と解説
問1からそのまま貼っていきます。コンビニの冷やし中華のタレを机の上にこぼすぐらいの疲れっぷりで貼り付けていますので、貼り付けミスなどありましたらご容赦ください。
問1の解説
問1の「複数の説明変数からガンの発症確率を推定するモデルを構築する分析手法」についての問題の解答はエです。
なぜなら、この問題では「年齢」「飲酒の頻度」「喫煙本数」という複数の説明変数を用いて、「ガンの発症の有無」という2値の結果(目的変数)が起こる確率を推定するモデルを構築しています。このような分析にはロジスティック回帰分析が適しているためです。[1][2][3][4][5] ロジスティック回帰分析は、結果が「はい/いいえ」「成功/失敗」「購入/非購入」などの2つのカテゴリに分類される場合に、それぞれのカテゴリに分類される確率を予測する統計的手法です。[1][6] 医療分野での病気のリスク予測や[1][3][4][7]、金融分野でのローン審査[7][8]、マーケティング分野での顧客行動予測(購入確率、解約確率など)[1][4][7][9] といった幅広い分野で活用されています。[4][8]
他の選択肢について:
- ア ABC分析: 在庫管理などで用いられる手法で、商品を売上高や重要度などに応じてA、B、Cのランクに分けて管理するための分析手法です。[10] パレート図などを利用して重点管理対象を特定する際に使われます。今回の問題のような確率予測モデルの構築には適していません。
- イ クラスター分析: データを属性の類似性に基づいてグループ(クラスター)に分ける手法です。[11][12][13] 例えば、顧客を購買履歴や属性によっていくつかのグループに分類し、それぞれのグループの特徴を把握する際に用いられます。[11] 教師なし学習に分類され、あらかじめ決まった目的変数(今回ならガンの有無)を予測するのではなく、データの中から構造を見つけ出すことを目的とします。
- ウ 主成分分析: 多数の変数がある場合に、それらの情報をできるだけ損失しないように、より少ない数の合成変数(主成分)に要約する手法です。[11][12] データの次元削減や、変数間の関係性を把握するために用いられますが、特定の目的変数の確率を予測するモデルではありません。[10]
補足:ロジスティック回帰分析は、線形回帰分析と名前が似ていますが、線形回帰分析が連続値(例:売上高、身長など)を予測するのに対し、ロジスティック回帰分析はカテゴリ変数(特に2値変数)の発生確率を予測する点で異なります。[3][6]
問2の解説
問2の「業務改善のフレームワークであるECRSに関する記述」についての問題の解答はウです。
なぜなら、ECRSは業務改善を進める上での4つの原則の頭文字をとったもので、以下の順番で検討することが推奨されています。[14][15][16][17]
- E (Eliminate): 排除・廃止 – その業務自体をなくせないか?[14][15][16][17][18][19][20]
- C (Combine): 結合・統合 – 複数の業務や工程を一つにまとめられないか?[14][15][16][17][18][19][20]
- R (Rearrange): 再配置・順序変更 – 作業手順、場所、担当などを変更して効率化できないか?[14][15][16][17][18][19][20]
- S (Simplify): 単純化・簡素化 – 業務をもっと簡単な方法にできないか?[14][15][16][17][18][19][20]
選択肢ウの「無駄な業務を排除していくことによって、事務工数を削減し、業務効率を上げる」は、ECRSの最初の原則である「E (Eliminate): 排除」に合致する内容です。[18]
他の選択肢について:
- ア: 「業務を簡素化することによって、担当作業者ごとの品質の差を無くしたり、ミスの防止につなげたりすること」は、「S (Simplify): 単純化」の視点です。[18][20] 選択肢では「C (Combine)」とされているため誤りです。
- イ: 「作業工程順序や作業場所、担当作業者を入れ替えることによって、業務の効率向上を図ること」は、「R (Rearrange): 再配置・順序変更」の視点です。[18][20] 選択肢では「S (Simplify)」とされているため誤りです。
- エ: 「類似している業務を統合していくこと」は「C (Combine): 結合」の視点です。[18][20] 「その逆に異なる属性を有する業務を分離すること」はECRSの原則には直接ありませんが、業務見直しの一部ではあります。しかし、選択肢全体を「R (Rearrange)」の視点としているため誤りです。
補足:ECRSは、製造業の現場改善(カイゼン)活動から生まれた考え方ですが、現在では製造業に限らず、オフィス業務やサービス業など、あらゆる業種の業務改善に適用できる汎用的なフレームワークとして活用されています。[15][17][21][22] ECRSを適用することで、コスト削減、生産性向上、ミスの削減などの効果が期待できます。[14][16][17][20]
以上が問1と問2の解説です。
問3の解説
問3の「顧客データと購買履歴データを用いて、商品の購入可能性が最も高いセグメントを予測する分析手法」についての問題の解答はエです。
なぜなら、この問題では「性別、年齢層、職業、年収」といった複数の顧客属性(説明変数)を組み合わせて顧客をグループ化(セグメント化)し、それぞれのセグメントが将来「商品を購入するかどうか(購入可能性)」という結果(目的変数)を予測しています。 このように、複数の条件(属性)に基づいてデータを分類・予測するのに適した手法が決定木分析だからです。 決定木分析は、データを木のような構造で表現し、「もし年収が〇〇以上で、かつ年齢層が△△なら、購入可能性が高い」といった形で、どの属性の組み合わせが特定の結論に至るかを視覚的にわかりやすく表現できます。 マーケティング分野において、ターゲット顧客の特定やキャンペーンの効果予測などによく用いられます。
他の選択肢について:
- ア ABC分析: 問1でも触れましたが、主に在庫管理などで重要度に応じてランク付けする手法であり、顧客セグメントの購入可能性予測には適していません。
- イ SWOT分析: 企業の戦略立案のために、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理・分析するフレームワークです。 データ分析手法というよりは、現状分析や戦略策定のツールです。
- ウ 競合分析: 市場における競合他社の製品、価格、戦略などを分析する手法です。自社の顧客分析や購入予測に直接用いられるものではありません。
補足:決定木分析は、データマイニングの代表的な手法の一つです。 問1で出てきたロジスティック回帰分析も予測に使われますが、決定木は結果に至るまでの分岐ルールが明確で解釈しやすいという特徴があります。
問4の解説
問4の「DCF法によるIT投資プロジェクトの金銭的価値の算定」についての問題の解答はアです。
なぜなら、DCF(Discounted Cash Flow)法は、将来にわたって得られるキャッシュフローを、定められた割引率を使って現在の価値に換算(割り引く)し、その合計額から初期投資額を差し引いて、投資の価値(正味現在価値: NPV)を評価する手法だからです。
問題の条件に基づいて計算してみましょう。
- 割引率: 20% (0.2)
- 初期投資: -150 百万円
- 各年のキャッシュフロー: 100 百万円
- 計算ルール: 年度ごとに百万円未満を切り捨て
- 1年後のキャッシュフローの現在価値:100 / (1 + 0.2)^1 = 100 / 1.2 = 83.333…
百万円未満切り捨て → 83 百万円 - 2年後のキャッシュフローの現在価値:100 / (1 + 0.2)^2 = 100 / 1.44 = 69.444…
百万円未満切り捨て → 69 百万円 - 3年後のキャッシュフローの現在価値:100 / (1 + 0.2)^3 = 100 / 1.728 = 57.870…
百万円未満切り捨て → 57 百万円
これらの現在価値を合計し、初期投資額を考慮してNPVを計算します。
- NPV = (1年後の現在価値) + (2年後の現在価値) + (3年後の現在価値) + (初期投資)
- NPV = 83 + 69 + 57 + (-150)
- NPV = 209 – 150 = 59 百万円
この計算結果(1年後: 83, 2年後: 69, 3年後: 57, 合計: 59)と一致するのは、選択肢の表 a です。
他の選択肢について:
- b: 3年後の計算(62)や合計(66)が異なります。割引計算か切り捨てのタイミングが違う可能性があります。
- c: 2年後の計算は合っていますが、3年後(83)や合計(99)が異なります。割引計算自体が間違っている可能性があります。
- d: 2年後(96)、3年後(99)、合計(128)がいずれも異なります。割引計算がされていないか、全く異なる計算をしている可能性があります。
補足:DCF法は、投資判断において時間的価値(今日の100万円は1年後の100万円より価値が高い)を考慮できる重要な手法です。割引率の設定(資本コストや期待収益率を反映)が評価結果に大きく影響します。
以上が問3と問4の解説です。
問5の解説
問5の「ODMにおける委託者と受託者の役割分担」についての問題の解答はエです。
なぜなら、ODM(Original Design Manufacturing)とは、受託者が製品の設計・開発から製造までを担当し、委託者はその製品を自社ブランドで販売する形態を指すからです [1, 3, 4, 5, 8]。 つまり、設計と製造の主体は受託者であり、販売の主体は委託者となります。
選択肢エは、「設計:受託者」「製造:受託者」「販売:委託者」となっており、ODMの役割分担を正しく示しています。
他の選択肢について:
- ア: 設計(委託者)、製造(委託者)、販売(受託者) の分担は、一般的な委託・受託モデルとは異なります。
- イ: 設計(委託者)、製造(受託者)、販売(受託者) は、設計を委託者が行い、製造と販売を受託者が行う形態で、これもODMとは異なります。製造のみを受託するOEM(Original Equipment Manufacturing)に近いですが、販売まで受託者が行うのは一般的ではありません [1, 5]。
- ウ: 設計(受託者)、製造(委託者)、販売(委託者) は、設計を受託者が行い、製造と販売を委託者が行う形態で、ODMとは異なります。
補足:
- OEM (Original Equipment Manufacturing): 委託者が製品の設計を行い、受託者はその仕様に基づいて製造のみを行う形態です [1, 5]。ODMと混同しやすいので注意が必要です。
- ODMのメリットとしては、委託者側は設計・開発のリソースがなくても自社ブランド製品を持つことができ、受託者側は設計能力を活かして付加価値の高いビジネスができる点が挙げられます [8, 26]。
問6の解説
問6の「バリューチェーンの説明」についての問題の解答はアです。
なぜなら、バリューチェーンとは、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱したフレームワークであり、企業の事業活動を、製品やサービスが顧客に届くまでの**価値(Value)**を生み出す一連の流れ(Chain)として捉える考え方だからです [2, 6, 7, 9, 13, 15, 19]。
具体的には、企業の活動を、価値創造に直接関わる「主活動」(購買物流、製造、出荷物流、販売・マーケティング、サービスなど)と、主活動を支える「支援活動」(全般管理(インフラストラクチャ)、人事・労務管理、技術開発、調達活動など)に分類します [2, 6, 13, 16]。 そして、どの活動工程でどれだけの付加価値が生まれているかを分析し、企業の競争優位性の源泉を探ったり、コスト削減や事業改善のポイントを見つけたりするために活用されます [2, 6, 13, 15, 19]。
選択肢アは、「企業活動を、五つの主活動と四つの支援活動に区分し、企業の競争優位の源泉を分析するフレームワーク」と述べており、バリューチェーンの定義と目的を正しく説明しています。
他の選択肢について:
- イ: 「企業の内部環境と外部環境を分析し、自社の強みと弱み、自社を取り巻く機会と脅威を整理して明確にする手法」は、SWOT分析の説明です [10, 11, 14, 20, 22]。
- ウ: 「財務、顧客、内部ビジネスプロセス、学習と成長の四つの視点から企業を分析し、戦略マップを策定するフレームワーク」は、**バランススコアカード(BSC)**の説明です [12, 17, 18, 21, 25]。
- エ: 「商品やサービスを、誰に、何を、どのように提供するかを分析し、事業領域を明確にする手法」は、事業ドメインの定義や、3C分析(顧客・競合・自社)などに近い考え方ですが、バリューチェーンそのものの説明ではありません。
以上が問5と問6の解説です。
問7の解説
問7の「コンテンツマーケティングの説明」についての問題の解答はウです。
なぜなら、コンテンツマーケティングとは、ターゲット顧客(潜在顧客や既存顧客)にとって**価値のある、有益な情報(コンテンツ)**を制作・提供し続けることで、顧客の関心を引きつけ、信頼関係を築き、最終的に自社の商品やサービスの購買、そしてファン化につなげることを目的としたマーケティング手法だからです。[18][19][20][21][22][23][24] 選択肢ウは、「潜在顧客に向けて、価値のあるコンテンツを作成し、情報発信することによって、潜在顧客との関係性を深め、最終的に自らの製品・サービスの購入につなげる手法」と述べており、このコンテンツマーケティングの核心を正確に捉えています。
他の選択肢について:
- ア: 著作権者からコンテンツを預かり、販売収益から利益を配分するのは、ライセンスビジネスやコンテンツ配信プラットフォームのモデルに近いです。
- イ: Web、テレビCM、新聞広告などを用いて企業側が伝えたいコンテンツを一方的に発信する手法は、従来の広告・宣伝(アウトバウンドマーケティング)に分類されます。[20] コンテンツマーケティングは、顧客を引きつける(インバウンドマーケティング)アプローチを重視します。[19][21]
- エ: 動画共有サイトで自主制作コンテンツを継続的に公開し、ファンコミュニティを形成して広告料収入を得る手法は、インフルエンサーマーケティングや動画クリエイターの収益モデルに近く、コンテンツマーケティングの目的である「自社製品・サービスの購入につなげる」とは主眼が異なる場合があります。
補足:コンテンツマーケティングで提供されるコンテンツは、ブログ記事、動画、SNS投稿、ホワイトペーパー、メールマガジンなど多岐にわたります。[18][21][22] 重要なのは、売り込み色を前面に出すのではなく、あくまで顧客にとって役立つ情報を提供し続けることで、中長期的な関係構築を目指す点です。[18][19][23]
問8の解説(訂正版2)
問8の「マーケティング戦略の策定プロセス」についての問題の解答はイです。
なぜなら、図に示されているマーケティング戦略の策定プロセスは、一般的に以下の順序(STP-MM)で進められます。
- 環境分析 (a): 市場や競合などを分析します。(選択肢ア)
- 市場細分化 (b): 市場をグループ分けします。(選択肢エ)
- ターゲット特定 (c): 狙う市場を決定します。(選択肢ウ)
- ポジション決定: ターゲット市場での立ち位置を明確にします。
- マーケティングミックス決定 (d): ポジションに基づき具体的な4P施策(製品・価格・流通・販促)を決定します。(選択肢イ)
- 実行計画策定: マーケティングミックスに基づき実行計画を立てます。
図のプロセス a → b → c → ポジション決定 → d → 実行計画策定 において、d は「ポジション決定」の後、「実行計画策定」の前に入るステップです。
STP(市場細分化→ターゲット特定→ポジション決定)の後に行うのは、具体的な施策であるマーケティングミックス(4P)の決定です。
したがって、**d に入るのは「イ マーケティングミックス決定」**となります。
※選択肢をうまく読み取れていなかったので再生成
問9の解説
問9の「需要の価格弾力性に関する説明」についての問題の解答はエです。
なぜなら、需要の価格弾力性とは、価格が変化したときに需要量がどれだけ変化するかを示す度合いのことです。[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]
- 弾力性が大きい(>1): 価格の変化率以上に需要量が変化する。価格を上げると需要が大きく減る(例:贅沢品、代替品が多いもの)。[35][37][40][41][43]
- 弾力性が小さい(<1): 価格が変化しても需要量はあまり変化しない。価格を上げても需要があまり減らない(例:生活必需品、代替品が少ないもの)。[35][37][40][41][43]
- 弾力性が1: 価格の変化率と需要量の変化率が同じ(単位弾力的)。[35][39]
選択肢エは、「必需品と贅沢品を比較した場合、一般に必需品の方が価格弾力性は小さい」と述べています。これは正しい説明です。生活必需品(米、トイレットペーパーなど)は、価格が上がっても生活に必要なため需要は大きく減りにくく、価格弾力性は小さい傾向があります。[36][37][40][41][43]
他の選択肢について:
- ア: 多くの競合他社が代替品を提供している場合、少し値上げしただけで顧客は代替品に流れるため、需要量は大きく変化します。つまり、価格弾力性は「大きく」なりやすいです。[34][37][43] 選択肢は「小さく」なりやすいとしているため誤りです。
- イ: 価格弾力性が大きい商品は、価格の変化に対して需要量が敏感に反応します。したがって、値上げをすると需要量は「大きく」減少します。選択肢は「大きな変化は見られない」としているため誤りです。[34][39]
- ウ: 価格弾力性の値が1の場合(単位弾力的)、価格を下げた変化率と「同じ割合」で需要量が増加します。[35][39] 需要量が変化しない(完全非弾力的)のは、価格弾力性が0の場合です。選択肢は「需要量は変化しない」としているため誤りです。
以上が問7から問9までの解説です。
問10の解説
問10の「ヘンリー・アサエルの購買行動類型における不協和低減型」についての問題の解答はウです。
なぜなら、ヘンリー・アサエルの購買行動類型モデルは、消費者の購買行動を以下の2つの軸で分類しているからです。
- 消費者と製品との関わりの程度(関与度): 高いか低いか。価格が高い、購入頻度が低い、失敗のリスクが高い製品などは関与度が高くなる傾向があります。
- 消費者がブランド間の違いを知覚できる程度: 高いか低いか。ブランドごとの特徴や品質に明確な差があると感じるかどうか。
このモデルにおいて、不協和低減型は以下の特徴を持つ購買行動です。
- 消費者と製品との関わり(関与度): 高
- ブランド間の違いの知覚: 低
つまり、消費者はその製品カテゴリー(例えば、カーペットや高価な家具など)に対して関心が高く、購入に慎重になるものの、どのブランドを選んでも品質や機能に大きな差はないと感じている状態です。
このため、消費者は比較的短時間で購入を決定することがありますが、購入後に「本当にこれでよかったのか?」「他のブランドの方がもっと良かったのではないか?」という**不安や後悔(認知的不協和)**を感じやすくなります。 そして、その不協和を低減するために、自分の選択を正当化する情報を探したり、製品の良い点を探したりする行動をとることがあります。
選択肢ウは、「どのブランドを購入すればよいか見分けがつかないまま購入し、その後にブランドの評価を行うので、購入後に何らかの後悔を感じる傾向がある」と述べています。これは、ブランド間の差をあまり知覚できない(見分けがつかない)が高関与のために購入後に評価し、後悔(不協和)を感じやすいという「不協和低減型」の特徴を的確に説明しています。
他の選択肢について:
- ア: 「他のブランドへの乗り換えにほとんど抵抗感がなく、目新しさや多様性を求めて、様々なブランドの製品を試しに購入する」は、関与度が低く、ブランド間の違いを知覚している(違いを求めて乗り換える)**「バラエティ・シーキング型」**の購買行動の説明です。
- イ: 「どのブランドも同じようだと感じるので、『いつも購入している』、『最初に目についた』、『単に知っている』などを理由に、特定のブランドを選ぶ傾向がある」は、関与度が低く、**ブランド間の違いをほとんど知覚していない「習慣購買型」**の購買行動の説明です。
- エ: 「まずブランド間の差異を認識した上で、様々な観点でブランド間の違いに関する分析・評価を繰り返した後に、最終的に購入するブランドを決定する」は、関与度が高く、**ブランド間の違いも高く知覚している「複雑な購買行動型」**の購買行動の説明です。
以上が問10の解説です。
問11の解説
問11の「バランススコアカードの戦略マップにおける特定の視点」についての問題の解答はエです。
なぜなら、問題文の記述は**「学習と成長の視点」**の特徴を明確に示しているからです。バランススコアカード(BSC)は、企業のビジョンと戦略を具体的な行動に結びつけるためのフレームワークであり、以下の4つの視点から業績を評価・管理します。
- 財務の視点: 最終的な財務目標(売上、利益、ROIなど)をどう達成するか。株主からどう見られているか。
- 顧客の視点: 顧客に対してどう行動すべきか。顧客満足度、市場シェア、新規顧客獲得など。
- 内部プロセスの視点: 顧客や株主を満足させるために、どのような業務プロセスを構築・改善すべきか。業務効率、品質、リードタイムなど。
- 学習と成長の視点: ビジョン達成のために、組織や個人の能力をどう向上させるか。従業員のスキル、情報システム、組織風土など。
問題文にある「無形資産は持続可能な価値創造の究極の源泉」「人材、技術及び組織風土が戦略を支える」「他の三つの視点の業績の先行指標である」という記述は、まさに「学習と成長の視点」が担う役割そのものです。 この視点での改善(例: 従業員のスキルアップ、情報インフラの整備)が、優れた内部プロセス(ウ)を生み、それが顧客満足(イ)につながり、最終的に財務成果(ア)に結びつくという因果関係が、戦略マップの基本的な考え方です。 そのため、「学習と成長の視点」は他の視点の成果を生み出すための基盤であり、先行指標と位置づけられます。
他の選択肢について:
- ア 財務の視点: 最終的な結果(遅行指標)を示すことが多く、無形資産や先行指標という記述とは異なります。
- イ 顧客の視点: 顧客満足度などが指標ですが、それを支えるのは内部プロセスや学習と成長です。
- ウ 内部プロセスの視点: 業務効率などが指標ですが、それを支えるのは学習と成長です。
問12の解説
問12の「マルチサイドプラットフォームのビジネスモデル」に関する問題の解答はアです。
なぜなら、マルチサイドプラットフォーム(多面プラットフォーム、MSP)とは、直接的なやり取りを求める複数の異なる顧客グループ(サイド)を結びつけ、そのグループ間の交流(トランザクションやコミュニケーション)を促進することで価値を創造し、収益を得るビジネスモデルだからです。 プラットフォームは、それぞれの顧客グループに対して異なる価値提案を行い、両者が存在することで互いに利益を得られるような「場」を提供します(ネットワーク効果)。 選択肢アは、「複数の異なる種類の顧客セグメントをつなぎ合わせ、顧客セグメント間の交流を促進する仕組みを提供するモデル」と述べており、このマルチサイドプラットフォームの核心的な特徴を正確に説明しています。
他の選択肢について:
- イ: 顧客との良好な関係構築やコミュニケーション支援は、CRM(顧客関係管理)の考え方に近いですが、複数の「異なる」顧客グループを結びつけるというMSPの必須要件を満たしていません。
- ウ: 川上(部品製造)と川下(販売)への進出は、垂直統合と呼ばれる戦略であり、プラットフォームモデルとは異なります。
- エ: 異なる機種やOSで動作するソフトウェアを提供するモデルは、クロスプラットフォーム戦略などと呼ばれます。利用者を増やす目的は同じかもしれませんが、異なる顧客グループ間の交流を主眼とするMSPの定義とは異なります。
補足:マルチサイドプラットフォームの例としては、以下のようなものがあります。
- 楽天市場: 出店者(売り手)と購入者(買い手)を結びつける。
- クレジットカード: カード会員と加盟店を結びつける。
- 求人サイト: 求職者と求人企業を結びつける。
- ゲーム機: ゲームプレイヤーとゲーム開発者(ソフトメーカー)を結びつける。
以上が問11と問12の解説です。
問13の解説
問13の「SCMから発展したS&OP(Sales and Operations Planning)の説明」についての問題の解答はウです。
なぜなら、S&OP(Sales and Operations Planning)とは、企業の**販売部門(Sales)と生産・供給部門(Operations)**が密接に連携し、需要予測と供給能力のバランスを取りながら、全社最適な事業計画(生産計画、在庫計画、販売計画など)を策定・実行していくための経営プロセスだからです。 SCM(Supply Chain Management)がサプライチェーン全体の効率化を目指すのに対し、S&OPは特に販売と生産の連携を強化し、市場の需要変動に柔軟に対応しつつ、経営目標(利益最大化など)の達成を目指します。
選択肢ウは、「新製品・既存製品の顧客重視型マーケティング計画(≒販売計画)と、サプライチェーンの管理(≒供給計画)とを融合して、継続的な競争優位性の確立に向けて戦略的に事業を推進する能力を経営者に提供する、戦略的計画の策定プロセス」と述べており、販売と供給(SCM)を統合し、経営戦略と結びつけるS&OPの考え方を的確に表しています。
他の選択肢について:
- ア: 顧客情報、見積もり、商談履歴などを管理し、営業プロセスを効率化する手法は、**SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)**の説明に近いです。
- イ: Webサイト、メール、SNSなどを活用したマーケティングやキャンペーン管理は、デジタルマーケティングや**マーケティングオートメーション(MA)**の領域です。
- エ: 製品の企画から廃棄までのライフサイクル全体にわたる情報を管理するプロセスは、**PLM(Product Lifecycle Management)**の説明です。
補足:S&OPを導入することで、需要と供給のミスマッチによる過剰在庫や品切れの削減、生産計画の安定化、部門間のコンフリクト解消、経営判断の迅速化・精度向上などの効果が期待されます。
問14の解説
問14の「技術経営における“魔の川”の説明」についての問題の解答はイです。
なぜなら、技術経営(MOT: Management of Technology)において「魔の川(Devil River)」とは、基礎研究や応用研究によって生み出された技術シーズ(研究成果)を、具体的な製品開発や事業開発の段階へと移行させる際に存在する大きな障壁のことを指すからです。 研究室レベルでは有望な技術であっても、それを実際の製品に応用し、開発プロジェクトとして立ち上げるまでには、技術的な課題、市場性の不確実さ、資金調達の困難さなど、多くの乗り越えるべき困難が存在します。
選択肢イは、「研究の結果を基に製品開発するまでの間に横たわる障壁」と述べており、まさにこの「魔の川」の定義と一致します。
他の選択肢について:
- ア: 研究の「開始まで」の障壁ではありません。
- ウ: 「事業化から市場での成功まで」の障壁は、一般的に**「ダーウィンの海(Darwinian Sea)」**と呼ばれます。市場投入後の激しい競争に打ち勝つことの難しさを指します。
- エ: 「製品開発から事業化まで」の障壁は、一般的に**「死の谷(Valley of Death)」**と呼ばれます。開発された技術や試作品を、実際に量産・販売し、ビジネスとして軌道に乗せることの難しさを指します。
補足:技術経営においては、この「魔の川」「死の谷」「ダーウィンの海」といった障壁をいかに乗り越えて研究開発の成果をイノベーションにつなげるかが重要な課題となります。それぞれの段階に応じたマネジメント(資金調達、マーケティング、組織連携など)が必要とされます。
以上が問13と問14の解説です。
問15の解説
問15の「エネルギーレビューのプロセスにおける“著しいエネルギーの使用の特定と特性の把握”」に関する問題の解答はアです。
なぜなら、エネルギーレビューのプロセスにおいて「著しいエネルギーの使用の特定と特性の把握」とは、エネルギーを多く消費している設備、プロセス、あるいはエネルギー効率に大きな影響を与えている要因は何かを突き止め、その特性(どのような条件下でエネルギー消費が増減するかなど)を理解する活動を指すからです。
選択肢アは、「生産施設、生産設備、生産プロセスなどの操業条件のうち、エネルギー使用量又はエネルギーパフォーマンスへの影響が大きい要素や関連する要素を明らかにすること」を述べており、まさにエネルギーを多く使用している箇所や要因(著しいエネルギー使用)を特定する活動に該当します。
他の選択肢について:
- イ: 省エネ技術やシステムの「導入の優先度を決定する」ことは、「エネルギーパフォーマンス改善の機会と優先度の決定」の活動内容に分類されます。
- ウ: 設備単位や工程単位での「きめ細かいエネルギー使用量を収集する」ことは、「エネルギーの使用及び使用量データの分析」を行うための前段階のデータ収集活動、あるいは分析そのものの一部と考えられます。特定そのものではありません。
- エ: 電気料金請求書などのデータに基づいて「エネルギー分析を行う」ことは、「エネルギーの使用及び使用量データの分析」の活動内容に分類されます。
補足:エネルギーマネジメントシステム(EMS)、特にISO 50001などでは、エネルギーパフォーマンスを継続的に改善するために、現状のエネルギー使用状況を正確に把握・分析する「エネルギーレビュー」が重要なプロセスとして位置づけられています。このレビューを通じて、効果的な省エネ対策を立案・実行するための基礎情報を得ることができます。
問16の解説
問16の「ティアダウンの説明」についての問題の解答はウです。
なぜなら、ティアダウンとは、競合他社などの製品を実際に分解・分析し、その構造、部品構成、材質、コスト、技術などを詳細に調査する手法だからです。 この分析結果を自社製品と比較することで、自社の強み・弱みを把握したり、コスト削減のヒントを得たり、より競争力の高い製品を開発するためのアイデアを得たりすることを目的とします。 リバースエンジニアリングの一環として行われることもあります。
選択肢ウは、「他社の製品を分解し、分析して自社の製品と比較することによって、コストや性能面でより高い競争力をもった製品を開発する手法」と述べており、ティアダウンの定義と目的を正確に説明しています。
他の選択肢について:
- ア: 「要求品質」と「技術特性」の2元表を作成し、顧客要求を満たす機能を明確にする手法は、**品質機能展開(QFD: Quality Function Deployment)**の説明です。
- イ: 整理・整頓によって事故防止や効率低下を防ぐ活動は、5S活動(整理、整頓、清掃、清潔、躾)の一部です。
- ウ: 物作りの仕組みの中の無駄を現場の知恵で排除する活動は、カイゼン活動や**IE(Industrial Engineering)**における改善活動の説明です。
以上が問15と問16の解説です。
問17の解説
問17の「サイバーフィジカルシステム(CPS)の説明」についての問題の解答はウです。
なぜなら、サイバーフィジカルシステム(CPS: Cyber-Physical System)とは、現実世界(フィジカル空間)にある様々なセンサーなどからデータを収集し、それをサイバー空間(コンピュータ上)で分析・処理・知識化し、その結果を使って現実世界をより高度に制御したり、新たな価値を創造したりする仕組みのことだからです。IoT(モノのインターネット)を発展させ、収集したデータを活用して現実世界へフィードバックする点が特徴です。
選択肢ウは、「現実世界のデータを収集し、仮想世界(サイバー空間)で分析・加工して、現実世界側にリアルタイムにフィードバックすることによって、付加価値を創造する仕組み」と述べており、CPSの基本的な概念を正確に説明しています。
他の選択肢について:
- ア: 1台のサーバ上で複数のOSを動かし、複数のサーバとして運用する仕組みは**仮想化(Virtualization)**技術の説明です。
- イ: 仮想世界を現実かのように体感させる技術で、人間の複数の感覚を刺激するものは**VR(Virtual Reality:仮想現実)**技術の説明です。
- エ: 電子データだけでやり取りされる、法定通貨のような強制通用力を持たない通貨は、**仮想通貨(暗号資産)**の説明です。
補足:CPSは、スマートファクトリー(工場の自動化・最適化)、自動運転、スマートグリッド(次世代送電網)、スマートヘルスケアなど、様々な分野での応用が期待されています。
問18の解説
問18の「J.コッターが提唱する“変革を生み出す”リーダーシップに求められる機能」についての問題の解答はウです。
なぜなら、ハーバード大学のジョン・P・コッター名誉教授は、リーダーシップとマネジメントを対比させて論じ、特にリーダーシップは「変革」を推進する役割を担うとしたからです。コッターによれば、リーダーシップの主な機能は以下の通りです。
- 方向性の設定: 将来のビジョンを描き、それを達成するための戦略を明確にする。(選択肢の「ビジョンの提示」)
- 人心の統合: ビジョンや戦略を人々に伝え、共感を得て、目標達成に向けて協力するように動機づける。(選択肢の「動機付け」)
- 動機付けと啓発: 困難に立ち向かうためのエネルギーを引き出し、人々の潜在能力を育成する。(選択肢の「コーチング」など)
これに対し、マネジメントは「複雑性への対処」を主な役割とし、計画立案、予算編成、組織設計、人員配置、統制(コントロール)、問題解決などを機能とします。
選択肢ウの「ビジョンの提示、動機付け、コーチング」は、まさにコッターが提唱する変革を生み出すリーダーシップの中心的な機能です。
他の選択肢について:
- ア、エ: 計画立案、組織の設計、人の配置、予算編成、問題解決、コントロールは、主にマネジメントの機能に分類されます。
- イ: 販売管理、財務管理、人事管理は、具体的な**管理(マネジメント)**業務の例です。
問19の解説
問19の「キャッシュフロー計算書における投資活動によるキャッシュフロー」に該当するものの問題の解答はエです。
なぜなら、キャッシュフロー計算書では、企業の現金の流れを以下の3つの活動区分で表示するからです。
- 営業活動によるキャッシュフロー: 企業の本業(商品やサービスの生産・販売、仕入、経費の支払いなど)から生じる現金の増減。
- 投資活動によるキャッシュフロー: 将来の利益獲得や企業価値向上を目的とした投資(固定資産の取得・売却、有価証券の取得・売却、貸付など)に関する現金の増減。
- 財務活動によるキャッシュフロー: 企業の資金調達や返済(借入れ・返済、社債の発行・償還、株式の発行(増資)、配当金の支払いなど)に関する現金の増減。
選択肢エの「有形固定資産の売却による収入」は、企業が事業のために保有していた固定資産(土地、建物、機械など)を売却して得た現金であり、これは設備投資の回収にあたるため、投資活動によるキャッシュフローに分類されます。
他の選択肢について:
- ア: 株式の発行による収入は、企業の資金調達にあたるため、財務活動によるキャッシュフローです。
- イ: 商品の仕入による支出は、本業の販売活動のための支出であり、営業活動によるキャッシュフローです。
- ウ: 損害賠償金の支払いは、通常、営業活動に関連して発生する(または臨時的な損失)と考えられるため、営業活動によるキャッシュフローに分類されるのが一般的です。
以上が問17、問18、問19の解説です。
問20の解説
問20の「債務超過の状態を表しているもの」についての問題の解答はアです。
なぜなら、債務超過とは、企業の負債の総額が資産の総額を上回っている状態を指すからです。 貸借対照表(バランスシート)においては、「資産 = 負債 + 純資産」という関係が成り立ちます。したがって、負債が資産を上回っている状態は、**「純資産合計がマイナスである」**ことと同義になります。
選択肢アは、この債務超過の定義(純資産がマイナス)を直接的に示しています。
他の選択肢について:
- イ: 負債合計が自己資本(≒純資産)よりも大きい状態は、多くの健全な企業でも見られます(レバレッジをかけている場合など)。必ずしも債務超過を意味しません。
- ウ: 負債合計が資本金よりも大きい状態も、利益剰余金などが十分に積み上がっていれば純資産はプラスであり、債務超過ではありません。資本金は純資産の一部に過ぎません。
- エ: 利益剰余金がゼロである状態でも、資本金や資本準備金があれば純資産はプラスになり得ます。債務超過とは限りません。
問21の解説
問21の「損益計算資料から当期の営業利益を計算する」問題の解答はイです。
なぜなら、損益計算書における営業利益は、以下の計算式で求められるからです。
営業利益 = 売上総利益 – 販売費及び一般管理費そして、売上総利益は以下の計算式で求められます。
売上総利益 = 売上高 – 売上原価
問題の表に示された数値を用いて計算します。
- 売上総利益の計算:売上高 (1,500) – 売上原価 (1,000) = 500 百万円
- 営業利益の計算:売上総利益 (500) – 販売費及び一般管理費 (200) = 300 百万円
したがって、当期の営業利益は300百万円となります。
他の選択肢について:
- ア (270), ウ (310): 営業外収益(40)や営業外費用(30)は、営業利益の計算には含めません。これらは経常利益の計算に使用します(営業利益 + 営業外収益 – 営業外費用 = 300 + 40 – 30 = 310 が経常利益)。
- エ (500): これは売上総利益(粗利)の金額です。
問22の解説
問22の「フェアユースの説明」についての問題の解答はエです。
なぜなら、フェアユース(Fair Use)とは、主に米国の著作権法などで認められている考え方で、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる特定の状況や条件を定めたものです。 これは、著作権者の権利保護と、社会全体の利益(学術、芸術、報道、教育などの発展)とのバランスを図るための仕組みです。 フェアユースと判断される主な利用目的として、批評、解説、ニュース報道、教育(教授)、研究、調査などが挙げられます。
選択肢エは、「批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方」と述べており、フェアユースの概念と主な適用場面を正しく説明しています。
他の選択肢について:
- ア: 公共の福祉目的による権利制限に関する考え方ですが、フェアユースそのものの定義ではありません。日本の著作権法にも教育目的などでの権利制限規定はありますが、フェアユースとは異なります。
- イ: 著作権使用料の徴収や著作権等管理事業に関する説明であり、フェアユースとは関係ありません。
- ウ: 著作物の内容や題号を勝手に変えてはいけないという、著作者人格権の「同一性保持権」に関する説明に近いです。フェアユースとは異なります。
補足:日本の著作権法には、米国のような包括的なフェアユース規定はありませんが、引用(32条)や、私的利用のための複製(30条)、教育機関における複製(35条)など、個別の権利制限規定が定められています。
以上が問20、問21、問22の解説です。
問23の解説
問23の「プログラムの排他制御の不備によって、プロセスやスレッドが共有リソースに同時アクセスした場合に想定外の動作をする」という問題の解答はエです。
なぜなら、この問題が説明しているのは**レースコンディション(競合状態)**と呼ばれる状況だからです。レースコンディションは、複数のプロセスやスレッドが共有リソース(メモリ、ファイルなど)に対して適切な排他制御(同時アクセスを防ぐ仕組み)なしにアクセスし、その処理の実行タイミングや順序によって結果が意図しないものになってしまう問題です。 まさに「競争(Race)」するようにリソースにアクセスした結果、予期せぬ状態(Condition)に陥ることからこのように呼ばれます。
他の選択肢について:
- ア クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF): Webアプリケーションの脆弱性の一つで、ログイン中のユーザーに意図しないリクエスト(例えば、パスワード変更や送金など)を攻撃対象のWebサイトに送信させる攻撃手法です。
- イ ディレクトリトラバーサル: Webサーバの脆弱性を利用して、公開されていないはずのディレクトリやファイルに不正にアクセスする攻撃手法です。パス名の操作によって上位ディレクトリへ移動しようとします。
- ウ バッファオーバーフロー: プログラムが確保しているメモリ領域(バッファ)のサイズを超えるデータを書き込もうとすることで、メモリ上の他の領域(戻りアドレスなど)を破壊し、不正なコードを実行させたり、システムを停止させたりする攻撃手法または脆弱性です。
問24の解説
問24の「JPCERT/CC CSIRTガイドにおけるベンダーチームの機能とサービス対象」の組み合わせについての問題の解答はウです。
なぜなら、JPCERT/CCのCSIRTガイド(※最新版も同様の考え方)では、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)をその機能やサービス対象によって分類しており、「ベンダーチーム」(PSIRT: Product Security Incident Response Team とも呼ばれる)は、自社が開発・提供する製品やサービスに関するセキュリティインシデント(特に脆弱性)に対応するチームと位置づけられているからです。 その主な機能は、自社製品の脆弱性情報を受け付け、分析し、修正パッチを作成・提供したり、利用者に対して注意喚起を行ったりすることです。 したがって、そのサービス対象は、自組織(製品開発部門など)及び自社製品の利用者となります。
選択肢ウは、この「自社製品の脆弱性に対応し、パッチ作成や注意喚起を行う」機能と、「自組織及び自社製品の利用者」というサービス対象の組み合わせを正しく示しています。
他の選択肢について:
- ア: CSIRT間の情報連携や調整を行うのは、主に「コーディネーションセンター」のような役割を持つCSIRTです。
- イ: インシデント傾向分析やマルウェア解析、攻撃痕跡分析などを専門に行うのは、「分析センター」のような役割を持つCSIRTです。
- エ: 組織内CSIRTの機能を有償で外部組織に提供するのは、「サービスプロバイダ」型のCSIRTです。
補足:CSIRTは、組織の種類や目的によって様々な形態があります。JPCERT/CCのガイドでは、主に以下のタイプに分類されています。
- 組織内CSIRT
- インターナルCSIRT
- コーディネーションセンター
- 分析センター
- ベンダーチーム(PSIRT)
- インシデントレスポンスプロバイダ
問25の解説
問25の「デジタルフォレンジックスに該当するもの」についての問題の解答はエです。
なぜなら、デジタルフォレンジックス(Digital Forensics)とは、コンピュータやネットワークなどのデジタル機器に残された記録(ログ、ファイル、メモリ情報など)を収集・保全・分析し、不正アクセス、情報漏洩、その他のサイバー犯罪などに関する法的な証拠を発見・特定・解明するための一連の技術や手続きのことだからです。「法廷における証拠」として扱えるように、データの収集・保全・分析のプロセスにおいて、正当性や完全性を担保することが重要視されます。
選択肢エは、「犯罪に関する証拠となり得るデータを保全し、調査、分析、その後の訴訟などに備える」と述べており、デジタルフォレンジックスの目的と活動内容を的確に説明しています。
他の選択肢について:
- ア: デジタルコンテンツに著作権者情報などを埋め込む技術は**電子透かし(Digital Watermarking)**です。
- イ: システムの弱点を発見するために実際に攻撃を試みるテストは**ペネトレーションテスト(侵入テスト)**です。
- ウ: 巧みな話術や心理的な手法でパスワードなどの重要情報を聞き出す行為はソーシャルエンジニアリングです。
以上で、お預かりした全問題の解説が終了しました。
使用したプロンプト
なお、解答の作成については以下が使用したプロンプトとなります。参考になるかは分かりませんが共有させて頂きます。(こちらを最初に書いた後、順番に画像で問題を渡してます)
私はITストラテジスト試験について勉強しています。あなたはプロフェッショナルの知識を持ったAIです。
午前Ⅱ試験の振り返りをしたいので、これから問題文と選択肢を順番に画像であなたにお渡ししますので、順番に解答と解説を書いてください。
なお、形式は「問1の〇〇についての問題の解答は〇です。なぜなら・・」という形で説明をしてください。他の選択肢や補足知識についてもよろしければ教えてくださいね。
また、解答用紙には私の書いた答えも書いてありますが、これは解説が終わった後に最後に合っているのかどうか教えてください。(解説のなかに私の選択肢がどうかを含める必要はありません。)
問題は1問、または2問ずつお渡ししますのでお渡しした分をまとめて答えてください。よろしくお願いいたします。
私は昨年2024年の4月にITパスポートを勉強・受験するところからはじめて、4月にITパスポート、(たしか)6月に基本情報、10月に応用情報とハイペースでの勉強をしています。ほとんど独学なので、これだけ勉強を進めることが出来たのは生成AIのおかげだなと本当に感謝しています。特にGoogleAIスタジオで最新のgeminiを無料で使えることが出来たのは本当にありがたかったです。
今回は受験した本番のテストをgeminiに解説してもらいましたが、いつもこんな感じで過去問を解き解説をしてもらっています。IPAのウェブサイトで無料で過去問のPDFが見られるのでとてもコスパが良いです。資格試験の参考書って本当に高くて、ただでさえ受験費用もかかりなかなか手が出ないので…。
AIについては様々な意見がありますが、私は人間が勉強して力をつけて、人間にしか出来ないことをするうえでAIはとても心強い存在だと思います。人間とAIが協調して素敵な未来が生まれていくといいな…と漠然と思います。
まとめ&参考書など
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。私は独学で試験に臨んでいたので、勉強はすべてgeminiにサポートしてもらいながら頑張っていました。もちろんITストラテジスト試験教官という観点で完璧というわけでもありませんが、自分が設定したケースに沿って様々なアドバイスをしてくれて本当にありがたかったです。
geminiだけだとちょっと話が一般論に偏りすぎるので、参考書も一通り目を通しておくのがおすすめです。私は新しいものはちょっと高かったので、ブックオフで古いものを買ったり色々組み合わせて勉強しておりました。広田先生のテクニックがとても分かりやすいのですが、ちょっと技巧的すぎる面もあるかな?と感じたので、広田先生の本+アイテックのオレンジの本(スタンダードな解説です)の組み合わせがおすすめです。広田先生の本は論文だけの薄いものでも基本的に同じことが書かれているので大丈夫かと思います。参考になりましたら幸いです。
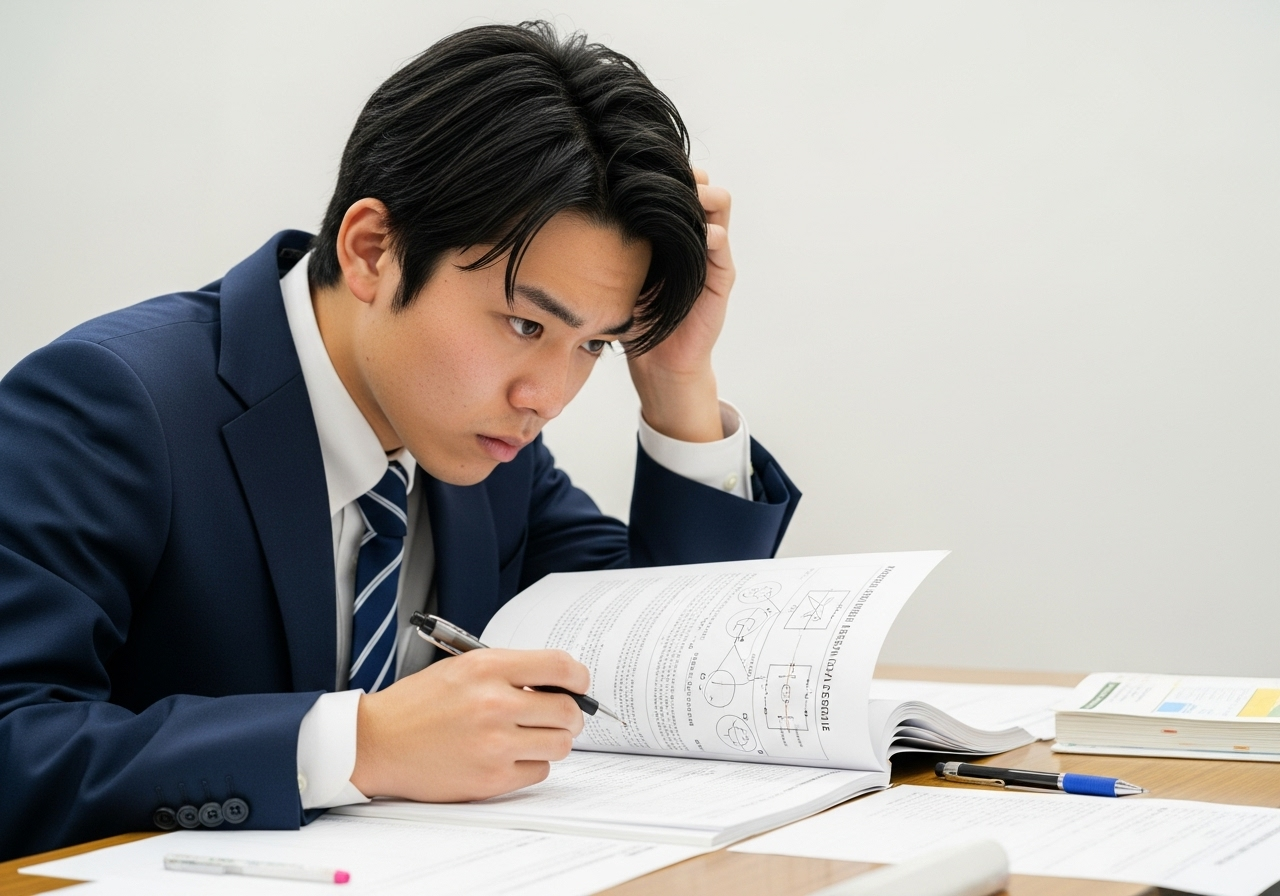



 (情報処理技術者高度試験速習シリーズ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51gxwPdF1zL._SL160_.jpg)




コメント